日産は中国での東風との合弁事業を通じて、世界最大の自動車市場で存在感を維持しようと積極的に動いています。その答えが「東風日産N7」、中大型の電気セダンで、最先端技術と十分な航続距離を驚くほどリーズナブルな価格で提供することを約束しています。今回はそのスペックを詳しく見て、この勝負が成功する可能性があるか検証してみましょう。
日産N7:東風の中国市場における電動車戦略
東風日産の旗印の下で発表されたN7は、単なる電気自動車ではありません。2027年までに30の新モデルを発売することを目指す日産の「The Arc」計画の重要な一翼を担う存在です。Dセグメントのこのセダンは中国市場専用で、2025年に生産開始予定。日本ブランドとしては中国での地盤回復に向けた戦略的な一手を示しています。日産が速やかな適応の必要性を認識した証ともいえ、中大型ピックアップのハイブリッドなど他の電動化施策は他市場ではまだ初期段階にある状況です。

N7は東風が開発した新しいモジュラーアーキテクチャ「天眼(Tianyan)」を初導入。このプラットフォームは柔軟性があり、純電気自動車(EV)だけでなくプラグインハイブリッド(PHEV)や航続距離延長型電気自動車(EREV)もサポート可能です。将来的にはこのアーキテクチャをベースにしたバリエーションの登場も予想されますが、現状はN7が純EVとして中国の消費者に魅力的なパッケージを提供することにフォーカスしています。
デザインとサイズ:空力を意識したエレガンス?
全長4,930 mm、ホイールベース2,915 mmのN7は、広々としたセダンでファミリーからビジネスユースまで幅広く対応。Dセグメントにしっかり位置づけられ、中大型セダンと競合します。ラゲッジ容量は床下スペースを含め504リットルと実用性も高いです。
デザインは日産の「Vモーション」デザイン言語をEV向けにアレンジ。前面グリルは完全に閉鎖され流麗なラインが特徴的です。ドアハンドルは埋め込み式で、全体的に非常に低い抗力係数(Cd値)0.208を実現。Carscoopsによれば、それは市場でもトップレベルの空力性能であり、高級モデルのメルセデスEQ Sと比べても一部で上回るほど。しかしながら、省エネ重視のEVによくある「個性が薄い」「味気ない」という声もあります。

ビジュアルハイライト
- フロントライトは710個のLEDを使用
- カスタマイズ可能な882個のOLEDリアランプ
- 埋め込み式のドアハンドル
- 17インチまたは19インチホイールを設定
テクノロジカルなインテリア:快適性と高い接続性
インテリアは価格以上の価値を感じさせます。注目は15.6インチの大型センターディスプレイ(2.5K解像度)で、強力なSnapdragon 8295Pチップを搭載。ArenaEVによると、このシステムは32GBのRAMと256GBストレージで、滑らかでレスポンシブなインフォテインメント体験を約束します。
快適性も抜かりなく、前席は49個のセンサーと12箇所のマッサージ機能を持つ「ゼロプレッシャーシート」、加えて調整可能なランバーサポートを備えます。上位グレードでは最大14個のスピーカー(パネル内蔵のリトラクタブルスピーカーも含む)を搭載したプレミアムサウンドシステムが提供され、高級感を演出します。

快適装備
- 50Wワイヤレス充電器
- 256色のアンビエントライト
- パノラマサンルーフ
- 内蔵冷蔵庫(−6℃から55℃まで調節可能)
パワートレイン:航続距離と性能
東風日産N7は前輪に永磁同期モーターを搭載し、前輪駆動(FWD)を採用。出力は160kW(218馬力)と200kW(268馬力)の2種類で、共に305Nmのトルクを発揮。トランスミッションはEVで一般的な単速です。
バッテリーは安全性と耐久性に優れるLFP(リン酸鉄リチウム)タイプで、容量は58kWhまたは73kWh。中国のCLTCサイクルによる航続距離は510kmから最大で635kmと発表されています。なおCLTCはWLTPやEPAよりも甘めの基準である点に注意が必要です。急速充電は3C対応で、10%から80%までわずか19分で充電が可能で、これは最新の急速充電技術に沿った性能です。
性能表
| 容量 | 航続距離(CLTC) | 0–100 km/h加速 | 最高速度 |
|---|---|---|---|
| 58 kWh LFP | 510 km | 8.5秒 | 160 km/h |
| 73 kWh LFP | 635 km | 6.9秒 | 160 km/h |
安全性と支援システム:AI搭載
N7にはモメンタが開発した高度運転支援システム(ADAS)「Navigate on Autopilot(NOA)」を搭載。高速道路や都市環境での半自動運転に加え、完全なインテリジェントパーキングも実現しています。CnEVPostの報告によれば、DeepSeek-R1というAI技術を統合し、運転者の意図認識や自然言語での対話が可能となり、車内体験を大幅に向上させています。

その他標準装備の支援機能としては、アダプティブクルーズコントロール、自動緊急ブレーキ、レーンキープアシストなどを搭載。興味深いのは、乗員の乗り物酔いを防止する支援システムも備えていること。前輪はマクファーソン式、後輪はマルチリンク式のサスペンションで微細な調整を行い、快適性を向上させています。
価格と競合:N7の価値は?
ここがN7の最大の強み(かつ挑戦点)です。中国での価格は11万9,900人民元から14万9,900人民元で、日本円換算すると約230万円から287万円ほど。この価格帯は、中国の確立された競合車種であるBYDハンやXpeng P7を大きく下回ります。約310万円から始まるBYDハンという直接競合がいる中、これほどの価格競争力は大胆な戦略といえます。
N7はパワーでは一部競合に劣り、駆動方式も前輪駆動のみですが、航続距離、搭載技術、低価格の組み合わせは中国の消費者にとって非常に魅力的でしょう。XPeng G9のような急速充電技術を活用しつつも、費用対効果に特化した投資と言えます。

簡易比較(BYDハン、Xpeng P7と比較)
| 特徴 | N7 73 kWh | BYD ハン EV 605 km | Xpeng P7 586 km |
|---|---|---|---|
| 価格(日本円換算) | 約230万〜248万円 | 約335万円 | 約390万円 |
| 航続距離(CLTC) | 635 km | 605 km | 586 km |
| 出力(kW) | 200 kW | 180 kW | 196 kW |
| 抗力係数 (Cd) | 0.208 | 0.230 | 0.236 |
長所と短所:検討すべきポイントは?
長所
- 非常に競争力のある価格設定
- セグメントトップクラスの航続距離(CLTC基準)
- 先進技術満載のインテリア
- 記録的な空力性能(Cd 0.208)
- 効率的な急速充電対応
短所
- 中国市場専用モデル
- 駆動方式は前輪駆動のみ(FWD)
- CLTC基準の航続距離はやや楽観的
- 効率重視ゆえの控えめなデザイン
前輪駆動(FWD)を選択したのは興味深いポイントです。多くのEVは後輪駆動(RWD)や四輪駆動(AWD)を採用し走行性能向上を狙いますが、FWDは生産コストを抑え、後席フラットフロア化により室内空間を広げられるメリットがあります。N7の価格帯においては合理的な選択ですが、スポーティーさを好むユーザーや、Tesla Model YのようなRWD/AWD搭載SUVと比べると方向性は異なります。

東風日産N7に関するよくある質問(FAQ)
FAQ
- 日産N7は中国以外で販売されますか?
現時点での輸出計画は発表されておらず、中国専用に開発されたモデルです。 - N7の実際の航続距離は?
最大635kmはCLTC基準の数値であり、より実際的なWLTPやEPA基準では450~550km程度と予想されます。 - AI搭載ADASは信頼できる?
モメンタやDeepSeekといった中国で信頼度の高い企業の技術を使っていますが、実際の信頼性は独立したテストや実使用で評価される必要があります。日産ニュースでは技術提携が詳細に述べられています。 - なぜ後輪駆動ではなく前輪駆動を選んだの?
生産コストを抑え、室内空間の広さや快適性を重視し、スポーティーさより実用性を優先したためと考えられます。 - 低価格は品質に影響する?
中国での現地生産、安価なLFPバッテリー採用、FWDの組み合わせで低価格を実現しています。内装の質感は高そうですが、耐久性や長期使用の信頼性は今後の評価が待たれます。Wikipediaの記事には各情報源からの詳細なデータが掲載されています。
東風日産N7は中国市場に特化した賢く計算された一手のようです。FWDによる走行性能のやや犠牲や大きく冒険しないデザインと引き換えに、先進的な技術や優れた(理論上の)航続距離、ほぼ無敵の価格を実現。都市生活者が重視する「広さ・技術・効率・コストパフォーマンス」を的確に捉えたクルマと言えます。もし品質や実使用経験がスペックに追いつけば、中国現地メーカーに対して十分に食い込む可能性があります。
皆さんは東風日産N7をどう思いますか?この積極的な価格戦略と技術重視の戦略は、中国市場の日産にとって成功すると思いますか?ぜひコメントで教えてください!














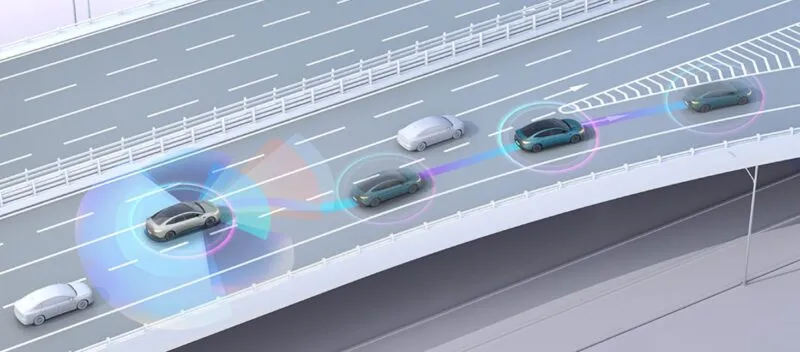


Author: Fabio Isidoro
Canal Carroの創設者兼編集長である彼は、自動車の世界を深く情熱的に探求することに専心しています。自動車とテクノロジーの愛好家として、質の高い情報と批評的な視点を融合させ、国内外の自動車に関する技術コンテンツや詳細な分析を執筆しています。








